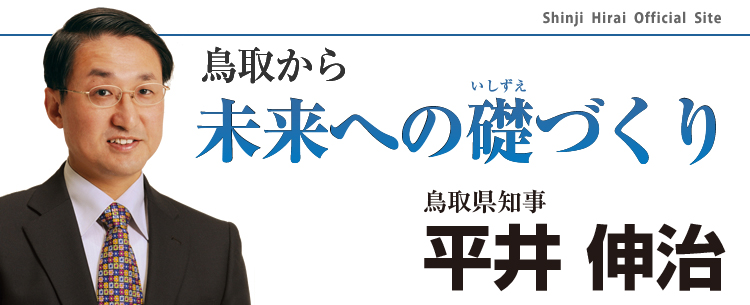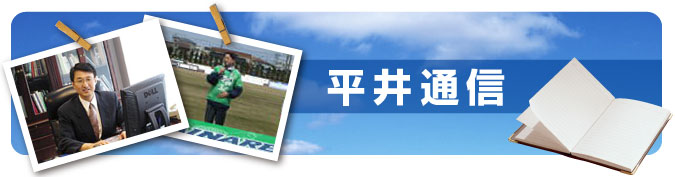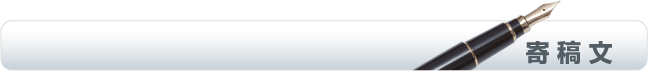
“The ballot is stronger than the bullet.”(投票は弾丸より強し)
近代民主主義を導いたリーダーとして名高いアメリカ大統領リンカーンの名言です。その時代のアメリカは南北戦争の真っただ中にあり、奴隷解放と民主主義死守のため戦った北軍勝利の司令官だったリンカーンも、皮肉なことに凶弾に倒れました。言わば、私たち人類は、多くの尊い命と引き換えに、民主主義と地方自治を普遍的価値として大切に発展させてきた歴史があります。その民主主義や地方自治は、ロシアによるウクライナ侵略など権威主義の台頭とともに力により脅かされる事態が今や世界で顕在化し、南北戦争の時代とは形を変えながらも危機にさらされているのかもしれません。大切な「価値」を私たちは後世へとしっかり引き継いでいかなければなりません。世界がインターネットで結ばれる今日、欧州議会議員選挙やアメリカ大統領選挙で国外からも含め情報戦が仕掛けられていると問題視されており、民主主義と地方自治を守るため精力的に連帯して行動を起こしていくことが急務となっています。
こうした外的要因や力による圧力と対峙する必要に加え、民主主義や地方自治が「内部から蝕まれる可能性」も決して看過できず、対策を講じていかなければなりません。
全国的に投票率の低下や議員のなり手不足などが深刻化しています。住民が投票や立候補を通じて民主主義や地方自治の根幹をなす意思決定に参画することが重要であるにもかかわらず、こうした選択や参画の機会を避けていく傾向が顕著になってしまうと、住民=有権者の意思と自治体行政や国政での政策選択・施策運営とが乖離してしまいかねません。これでは民主主義や地方自治を手にしていても、真の恵沢が人々にもたらされなくなってしまいます。
更に、デジタル化が急速に進展し、産業や日常生活のみならず、民主主義や地方自治にも様々な影響を与え始めています。特に、爆発的に普及が進むAIは、膨大なデータを基に加工して流暢な文章や生成画像で出力するなど便利な反面、実はその答えを導くアルゴリズムの仕組みは複雑でかつブラックボックス化しており、人間のコントロールの及ばないところで大切な意思決定などが左右されてしまう可能性もあります。また、例えば、AIが扱っているのはネット上に提供されている情報であることから、引きこもりや各種団体の中で課題となっていることなど、行政が本来集めるべき情報が反映されないにもかかわらず、全ての情報がパソコンを叩けば瞬時に得られるという錯覚に陥り、機械に導かれるまま行政の使命を果たせなくなる危険もあります。
こうした喫緊の課題に立ち向かっていくため、鳥取県では、昨年、「投票率低下防止等に向けた政治参画のあり方研究会」(座長 慶應義塾大学谷口尚子教授)と「先端技術と民主主義のあり方を考える研究会」(座長 慶應義塾大学山本龍彦教授)を設置し、有識者や専門家等を交えながら調査研究を重ねてきました。その報告が今春まとまり、「投票率低下防止等に向けた政治参画のあり方研究会」では、民主主義の再興と主権者教育、投票環境の向上、議員のなり手不足についての方策を提言し、「先端技術と民主主義のあり方を考える研究会」では、全国自治体で初めて生成AI等についての報告をまとめ、「自治体デジタル倫理原則」や情報発信者を明示するオリジネーター・プロファイル活用などを提案しました。
投票率低下の原因となっていることに、全国で相次ぐ投票所閉鎖があげられます。公職選挙法において全ての投票所において2人以上5人以下の投票立会人を選任することが義務づけられていますが、中山間地域の市町村などでは投票立会人の確保が困難となっており、結局投票所を廃止せざるを得なくなる状況が生まれています。戦後の社会的混乱の中、投票立会人を複数設置して選挙の公正を期する意義はあったと思いますが、全ての投票所毎に配置すべき立会人の法定人数を確保できず、投票所を閉鎖せざるを得ないというのは本末転倒と言えるでしょう。「立会人を置く」ことより、有権者に身近な施設に「投票箱を置く」ことこそ優先すべきです。
「投票率低下防止等に向けた政治参画のあり方研究会」では、投票立会人制度の見直しを求めつつ、「デジタル技術を活用し、カメラ越しでの立会の試行導入なども行いながら検討を進めていくことで、投票立会人を柔軟に確保し、投票所を閉鎖することなく維持していけるようにすべき」と提唱しました。早速鳥取県では、このアイディアを全国に先駆けて実現するため、6月9日に予定される智頭町長選挙と議員補欠選挙でオンライン立会を導入する財政的・技術的支援に取り掛かりました。5月9日には、ICT端末としての機能を有し住基ネットと接続可能なコネクテッドカーによる巡回期日前投票でオンライン立会を行う実証リハーサルを実施しました。鳥取県の挑戦を前に、総務省はオンライン立会を事実上容認し実施上の留意点に関する通知を4月26日に発しましたが、これは大いに評価に値する勇断でした。鳥取県で声をあげ、民主主義と地方自治を守る挑戦のため法解釈を弾力化する対応を、国から引き出すことができました。
また、鳥取県としては、公職選挙法の投票立会人の必置人数等を見直すよう国に求めるべきと訴え、関西広域連合構成自治体等の賛同を得て、政府の地方分権改革推進会議に制度改革の提案を行ったところです。
「先端技術と民主主義のあり方を考える研究会」では、「人間主導のデジタル社会へ」を目指すべく、「自治体デジタル倫理原則」として、〈1〉住民自治の原則、〈2〉人権保障の原則、〈3〉インクルーシブの原則、〈4〉パートナーシップの原則、〈5〉課題解決志向の原則、〈6〉人間主導の原則、〈7〉リテラシーの原則、〈8〉透明性の原則、〈9〉ガバナンスの原則、〈10〉機敏性の原則からなる10項目を、自治体の先端技術への基本的向き合い方として提言しました。
まず初めに、住民自治の原則を掲げることにより「重要なことは人間が決める」という人間主導を基本としたことは、地域のことは住民の意思に基づき検討や議論を重ねて決定する民主主義や地方自治の要諦そのものです。
AIは、技術的限界等により、習得データの偏りなどが原因となって差別的な回答を示したり、個々人の具体的な事情を無視した統計的・確率的な回答を示したりしますが、これによる人権侵害のリスクも生じ、例えば、ネット上に溢れているジェンダー観等がそのまま回答に結び付くため、現状からの改革に繋がりにくいという問題点も国際的に指摘されています。政府は事業者向けの運用指針を策定しましたが、AI法を欧州連合が制定するなど国際社会が改革へピッチを上げる中、わが国ではAIと基本的人権、民主主義の関係に関わる議論が十分とは言えず、自治体関連の報道でも「AIを使ってみました」というものばかりクローズアップされています。シンギュラリティが現実味を帯びる中、新しい技術とどう向き合って、民主主義や地方自治という大切な制度が、技術のサポートで伸びることはあっても、技術によって支配されて人間が主導できない世界に陥ってしまうことのないよう、まずはデジタル社会を人間主導で運営する「倫理」を十分に議論し実践を重ねるべきだと考えます。かつて自動車が文明の利器として登場した後、モータライゼイションが急速に進み産業や日常生活に様々な恩恵をもたらしましたが、それと同時に安全に人と車が共存していくため順守すべき交通ルールが定められ、環境を守るための技術革新が重ねられてきました。デジタル技術についても、これと同様な進化の過程を、人類全体で考えていくべき段階に入ったと考えるべきでしょう。
鳥取県では5月7日に、全庁で「自治体デジタル倫理原則推進本部」を組織し、その尊重を求め、AIを含む先端技術の運用の指針に基づき実践を重ねていくプロジェクトに着手しました。
さて、今年は辰年です。鳥取県の地図を眺めてみてください。角を生やした竜が、西に頭を向けた形をしています。鳥取県は実は「竜の化身」…「とっとリュウ県」です。
県内には日本一長い竜の彫刻で有名な琴浦町の「神崎神社」や、山陰海岸ジオパークの名所で竜が棲むと伝わる岩美町の「龍神洞」など、竜のパワースポットが数多くあります。
今年は昇竜をとげる年。魅力満載の「とっとリュウ県」へ、ウェリューカム!