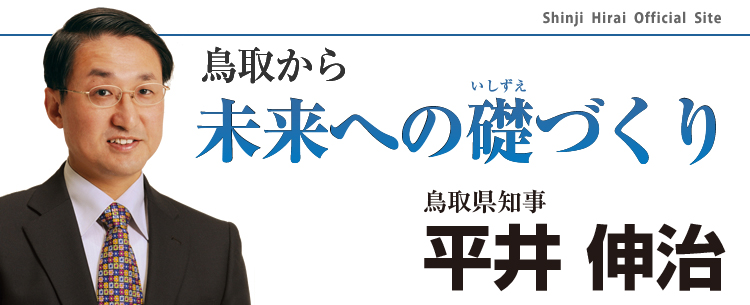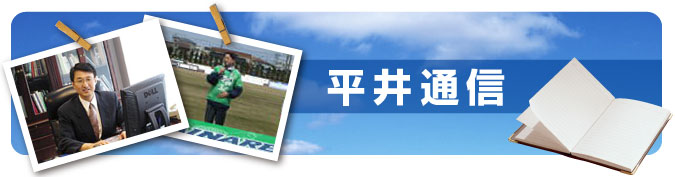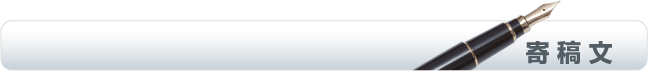
本年1月1日の能登半島地震で亡くなられた方々に心よりお悔やみ申し上げ、被災者にお見舞い申し上げる。国連グテーレス事務総長が「地球沸騰化」と叫ぶ中、昨年唯一上陸した台風7号は、8月15日夕刻本県に最接近。鳥取・八頭・三朝等で、激流による洗堀や流された岩の激突などで護岸崩壊が頻発した上、川沿いの道路や電線・上下水道等も巻き込み、道路途絶やライフライン切断に至った。各地で土砂災害も惹起し、被災は3千箇所を超え、農林被害も含め被害総額316億円の本県過去最大規模の水害となった。
昨年の台風7号上陸の日、気象庁は中国地方が1日最大雨量250㎜とし、報道機関は台風の進路予想や「進路の右側は危ない」として東海・近畿の中継を繰り返した。
鳥取は台風進路の左側だが、昭和36年第二室戸台風や昭和62年台風19号等、同様の進路で大災害を被った。今回もアウターバンドの雨雲が山陰で線状降水帯となり、15km/hと遅い台風に回り込む日本海からの風が雨雲を延々と供給。台風本体の雨雲も続く悪条件が重なる。
台風最接近を前に、長年の現場判断により、15日午後1時45に県災害対策本部会議を開き、私から、今回は危険な台風で「最近になく非常に厳しい状況も予測される」として、県民・関係機関に「避難を早めにする、命を守る、適切な災害対応を」と強く呼び掛けた。正直、気象台や報道の認識より大きく踏み込む呼び掛けは勇気を要した。果せるかな、3時間後に気象庁は大雨特別警報を鳥取市に発令し、観測連続雨量が鳥取市佐治で627㎜にも上った。
気象予報システムの全国運用が進む中、現場の判断や地域特有の条件に基づく知見こそ重要だ。当時の日本海の海面水温は27℃以上で平年より5℃くらい高かった。近年北風で運ばれる海面水蒸気が山に当たり豪雨が頻発していた。今年5月の日本気象学会で気象研究所の辻野智紀研究官らが、今次の特別警報の大雨は、日本海の高水温により、フェーン現象で高温乾燥した北陸からの風が海面で水蒸気を蓄え、鳥取県上空に回り込んで豪雨になったと発表した。地元の実情に合う災害激甚化の仕組みがようやく見えてきた。
台風7号が過去最大級の水害となったが、治水対策や国土強靭化に加え、地域住民が連携した避難対策等の成果で、氾濫は抑制され人的被害や住家被害は最小限にとどまった。
他方、土砂崩れ、護岸崩落、落橋等の激しい被害で道路が寸断され、28集落、1820人が孤立という危機に。一刻も早く孤立を解消することは、命と生活に関わる最優先課題だ。昼夜を分かたぬ応急復旧工事により18日には全ての孤立集落解消を実現した。この背景には行政・電力・通信等が連携し一括して地元業者と道路啓開等に当たる、小回りを生かした手法がある。
予算措置も15日夜から県議会要路と調整を始め、18日に議会代表者会議を経て補正予算を専決。小さな県だからこそ、機動力が出る。
台風7号災害の教訓を生かし創造的復興に着手し、能登半島地震を踏まえ、津波観測体制を整え、空・海からの救出拠点調整にかかる。災害激甚化へ、鳥取県の挑戦は続く。