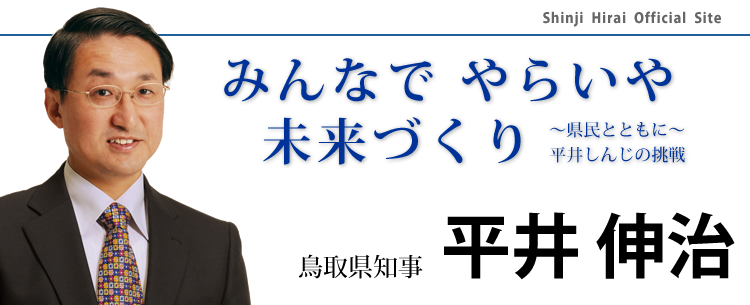〜平成23年4月の鳥取県知事選挙へ向けて〜 平成23年3月に作成
〜平成23年4月の鳥取県知事選挙へ向けて〜 平成23年3月に作成
老後の不安、健康の不安、生活の不安など、不安を感じる人が増えています。老若男女を問わず安心して暮らせるために、医療や福祉をはじめとした生活環境を整え、暮らしの安心実現に向け、県民目線・生活者の目線で取り組んでまいります。その前提となる災害対策・治安や社会資本充実など暮らしの基礎条件も、しっかりと固めてまいります。
鳥取ふれあい共生ホームなどの全県展開
障がい者・高齢者・児童等が住み慣れた地域でともに暮らしていく「鳥取ふれあい共生ホーム」を、発祥地西部だけでなく全県的に展開します。また、特別養護老人ホームの増床や小規模多機能型居宅介護事業所の整備を進め、待機高齢者を解消します。
健康長寿いきいき社会の推進
高齢者相互の支え合いボランティアを介護保険の割引対象等とする「介護支援ボランティア制度」を導入し、介護予防や地域のふれ合いを進めるとともに、高齢者の文化・スポーツ・ボランティアなどの諸活動を推進し、健康長寿をいきいきと満喫できる社会を作ります。また、介護現場の人手不足を解消し雇用の場として活用するため、国に対して介護報酬の適正化を求めていきます。
バリアフリー社会の実現
鳥取県で始まり全国に広がり始めた障がい者と健常者が支え合いバリアフリーを進める「あいサポート運動」を更に拡大し、10万人(現在2万5千人)体制を目指します。地域とふれ合いながら生活する地域生活移行を進め、施設入所者400人の移行を目指します。また、障がい者の処遇向上に効果が出た工賃3倍プロジェクトを継続遂行するとともに、鳥取県独自の農林水産業と福祉の連携による障がい者就労の拡大を図ります。
消費者相談ネット構築
消費者をねらった犯罪や多重債務問題など、消費者を支援するネットワークの構築が急がれます。そこで、市町村やNPOなどと連携した鳥取県独自の安心安全消費者相談ネットワークを確立し、広域連携による相談窓口の共同組織化を実現します。また、200人を目標として地域消費生活サポーターの養成を進めます。
「支え愛」まちづくりの展開
中山間地域見守り活動を企業等と行っていることは、全国から注目されています。更に、中山間地での防犯・防災対策、買い物難民対策、交通対策をはじめ、子どもたちや高齢者、障がい者等を含め、行政のみならず地域住民で主体的に支え合う「支え愛」まちづくりを進め、全国に誇り得る愛情と安心にあふれたモデル的な地域社会を形成します。そのため、全市町村への「支え愛」コーディネーターを配置する等、先導的な施策を市町村や住民と協力して展開します。
がん対策の戦略的推進
休日検診等の拡大など検診を受けやすい体制の充実によりがん検診の受診率を大幅に引き上げ、がんの早期発見につなげるとともに、人材養成や施設設備の充実を通じてがん治療の医療水準を向上させ、全国平均以下を目指してがん死亡率の改善を図ります。
安心医療体制の整備
医師・看護師不足を解消するため、大学等と共同して定員増や県内定着奨励など人材対策を進めるとともに、戦略的に病院間連携等を推進し、地域医療の持続的発展と高度化を図ります。また、特に高度な医療を必要とする場合に、他県の先進医療施設と連携するネットワークを構築するとともに、腎センターなど拠点整備を行います。
生活習慣病対策の推進
いきいきと健康な人生を送るため、食習慣の改善や運動習慣の定着、歯・口の健康維持など、生活習慣病の改善対策を進め、特定健診受診率・歯科検診受診率の向上や生活習慣病死亡者数の抑制を図ります。その一環として、ウォーキング等の普及や、若者層の禁煙治療費助成、学校と連携した禁煙指導の徹底を行います。
自殺対策推進
自殺予防に関する正しい知識の普及やうつ病対策等を関係機関と連携して実施することにより、自殺者数を現在よりも減らす実践活動に取り組みます。また、苦しみを余儀なくされている自死遺族の方々への支援も含め、自殺対策を積極的に推進します。
未来への社会資本整備
道路、港湾など交通基盤整備を推進するとともに、緊急豪雨対策が必要な59箇所の砂防事業を完遂します。浸水対策として河川拡幅、治水緑地整備、堤防強化を行うとともに、河川監視システムを整備するなど市町村等と連携して避難対策も強化します。
津波避難対策ほか危機管理強化など安心のふるさとづくり
東日本大震災での大津波被害や口蹄疫など、多様な事態へ機動的に対応する力が必要となってきました。県庁防災局を危機管理局に改組し危機管理事象への対処能力向上を図り、積雪を含む災害等の情報を集約して新たに災害情報ダイヤルを設ける等、住民に必要な情報を適時に提供できる体制を構築します。また、津波避難計画の策定、除雪対策などの新たな課題や自主防犯・防災対策についても、地域・国・市町村等と連携した取組を強化します。悲惨な交通事故を防止するため、信号機増設箇所数を従来より引き上げます。